大手企業は年間〇〇万円を知財に使ってます!【エレコム編】
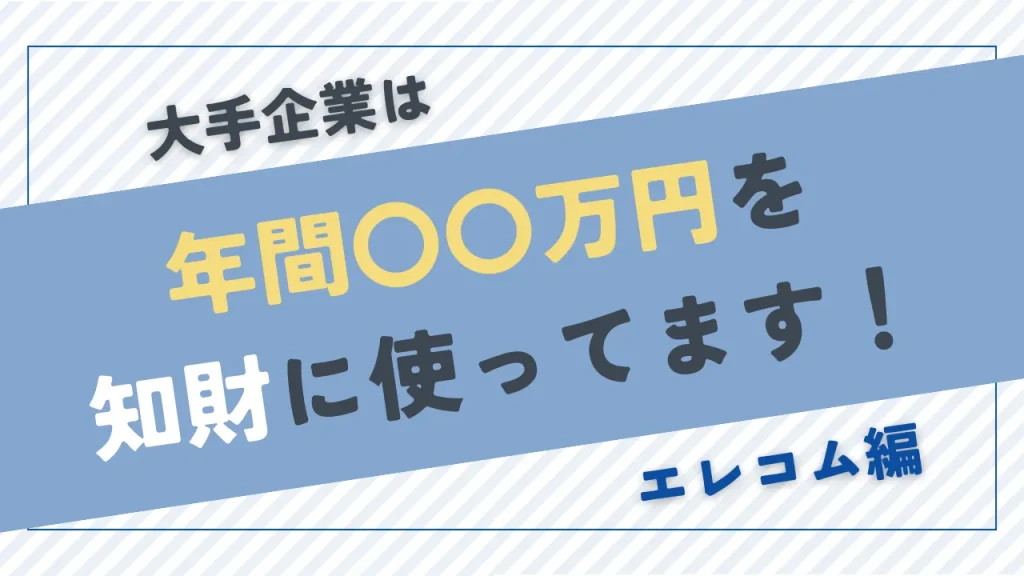
先日、公開したこちらの記事を読んで編集部は思いました。
エレコムが反射素材を使用したスマホ用ショルダーストラップを新発売。身近な商品もしっかり知財で保護
エレコムってそんなに知的財産権を保有しているの?と。
そして、こうも思ったのです。権利のためにすごい金額かけてそうだな…と。
なぜなら知的財産を「権利」にするためには、1件あたり十万円単位のお金が軽く消えていくからです。少なくとも特許で60万円、意匠で20万円、商標で15万円は必要です。
更に権利を存続させるためにもお金がかかります。
じゃあ実際のところ、エレコムは年間で知財にいくら使っているのか?編集部がリサーチをしました。
※権利化にかかる費用は度々更新されますが便宜上、全ての計算に最新の費用を適用させます。また小数点は全て四捨五入しています。
手始めに公式HPを確認してみたところ…
まずは公式HPを見て、決算書などにエレコムは知的財産でいくら使っているのか、が記載されてないか確認しましたが、あえなく撃沈。
そうすると、残された手段はJ-PlatPatというデータベースを利用して自力で算出するしかありません。
というわけでさっそくJ-PlatPatのページに行って検索・計算をしていきました。
なお最初にお断りしておくと、めちゃくちゃ長い記事になっちゃったので、最後まで頑張って読んでください!!!
特許からスタート!
まずは特許権取得にかかる費用の計算式を確認します。
- 出願時印紙代…14,000円
- 審査請求費用…138,000円+(請求項の数×4,000円)
- 登録料…12,900円+(請求項の数×300円×3年)
- 弁理士費用(目安)…30万円~
- 権利の維持費用…出願からの経過年数による
そして検索したところ、2022年に出願された特許は4件!これは比較的サックリ計算できそうです。
手始めに印紙代
印紙代の計算は、単純に件数をかけるだけ。14,000円×4件で、56,000円ですね。
審査請求費用
続いて審査請求費用です。4件のうち、審査請求されている出願は1件だけ(請求項の数は11)でした。
138,000円+(11項×4,000円)=182,000円(18万円)
登録料
ここで、2022年に登録となった出願を抽出するため検索条件を変更します。「登録日 20220101~20221231」という条件をプラスした結果、該当した特許は14件、請求項の数は合計で72にのぼりました。
12,900円×14件+(合計72項×300円×3年)=245,400円(24万円)
弁理士費用を計算!
さきほど、出願時の弁理士代は30万円~と紹介しましたが、請求項の数でも価格は上がりますし、中間処理という追加作業に伴う追加料金の発生が起きるケースもあります。
そういった諸々の値上がり分を考慮して、1.2倍した数字で計算をしていきました。
30万円×4件×1.2=1,440,000円(144万円)
ラスト、権利の維持費用の算出が予想外に面倒
ここで困った問題にぶち当たりました、権利の維持費用(特許年金)の計算です。端的に言うと、2022年に特許年金を支払った特許、を絞り込める気がしない!
そこで妥協案として、特許庁の公表している特許権の現存率を利用して計算してみました。
まずは権利が存続している件数(現存件数)を出していきます。
なお特許権登録時、強制的に3年分の権利費用を登録料として支払っているため、今回は2019年分から計算しています。また2009年以前は現存件数が0になる計算なのでスペースの都合上省略しました。また特許庁のデータを「登録から●年後の現存率」と解釈して表には記載をしています。
| 登録年(年) | 登録件数(件) | 現存率(%) | 現存件数(件) |
| 2019 | 3 | 96.6 | 3 |
| 2018 | 2 | 88.6 | 2 |
| 2017 | 1 | 84.7 | 1 |
| 2016 | 4 | 78.8 | 3 |
| 2015 | 3 | 69.5 | 2 |
| 2014 | 2 | 62.9 | 1 |
| 2013 | 1 | 53.7 | 1 |
| 2012 | 7 | 41.2 | 3 |
| 2011 | 2 | 32.3 | 1 |
| 2010 | 1 | 27.3 | 0 |
参考: 特許行政年次報告書2022年版 | 経済産業省 特許庁
次に請求項の数ですが、登録料の計算でつかった「14件で72項」というデータから1件あたり5項として計算を進めます。
詳しい特許年金の計算式はこちらの記事を見て頂くとして、
((10,300円+5項×800円)×6件)+((24,800円+5項×1,900円)×6件)+((59,400円+5項×4,600円)×5件)=703,600円(70万円)
という結果になりました。
特許編の合計金額は…
はてさて、特許編のまとめ・総額はいくらになるのか!ドン!
56,000円+182,000円+245,400円+1,440,000円+703,600円=2,627,000円
特許だけで262万円使っているようです。
しかし、まだ意匠と商標が待っています。引き続き計算していきましょう。
エレコムのメイン・意匠権
【意匠出願の費用 計算式】
出願時印紙代…16,000円
登録料…8,500円/年(第1年から第3年)、16,900円/年(第4年から第25年)
弁理士費用(目安)…17万円~
エレコムの持っている権利のなかでは意匠が一番多い!検索結果1210件にビビりつつ算出していきました。
印紙代と弁理士費用の計算はラクですね。弁理士費用だけ追加料金等を余分に見積もるため、1.2倍します。2022年の出願件数は36件なのでまとめて計算すると
16,000円×36件+170,000円×36件×1.2=7,920,000円
という結果に。出願だけで792万円です、特許と比べると突然数字が大きくなりましたね!
ちなみに2022年は出願件数が控えめな年です。最近だと2021年の122件出願が際立って多く、この年は印紙代+弁理士費用だけで2684万円かかってます。
登録料・権利維持費用がエグイ
こちらも、特許庁のデータを元に現存件数を出して計算しました。
ただ特許庁のデータは出願後15年目、までしか情報がありません。いちおう傾向からすると毎年5%ずつ減少しているようなので、1年毎に現存率が5%減すると仮定し計算しました(当該部分には※マークを付けています)。ほかの部分は特許編に準じています。
| 登録年(年) | 登録件数(件) | 現存率(%) | 現存件数(件) |
| 2022 | 88 | 100.0 | 88 |
| 2021 | 115 | 98.7 | 114 |
| 2020 | 98 | 95.7 | 94 |
| 2019 | 78 | 89.4 | 70 |
| 2018 | 79 | 79.7 | 63 |
| 2017 | 97 | 76.2 | 74 |
| 2016 | 100 | 70.3 | 70 |
| 2015 | 118 | 62.6 | 74 |
| 2014 | 75 | 57.7 | 43 |
| 2013 | 39 | 50.9 | 20 |
| 2012 | 43 | 45.8 | 20 |
| 2011 | 75 | 41.0 | 30 |
| 2010 | 38 | 35.0 | 13 |
| 2009 | 47 | 30.9 | 14 |
| 2008 | 15 | 25.5 | 4 |
| 2007 | 35 | 20.0※ | 7 |
| 2006 | 20 | 15.0※ | 3 |
| 2005 | 11 | 10.0※ | 1 |
| 2004 | 3 | 5.0※ | 0 |
意匠権は1~3年目が毎年8,500円、4~20年目までが毎年16,900円を支払います。
(88+114+94)件×8,500円+(70+63+74+70+74+43+20+20+30+13+14+4+7+3+1+0)件×16,900円=11,067,400円
権利の維持だけで1107万円、おそろしい数字が叩き出されました!
意匠にかけた総額は
7,920,000円+1,067,400円=18,987,400円
エレコムさんは意匠権の数が多いだけあって、1900万円と大きな金額が飛び出しています。
最後は商標の額を計算
ラストは商標の計算。2022年に出願されているのは18件です。
【商標出願にかかる費用】
出願費用…3,400円+(区分数×8,600円)
10年分の登録料…32,900円×区分数
10年ごとの更新手数料…43,600円×区分数
弁理士への手数料(目安)…10万円~
ひとまず出願費用を算出
まずは出願費用を出していきます。出願費用だけで飛ばしてます。
3,400円×18件+(合計36区分×8,600円)=370,800円
登録料の総額は?
お次は登録料です。「登録日 20220101~20221231」で検索しなおしたところ、ヒット件数は36件!区分数にして69件です。
なお商標権の登録料は5年分/10年分で選べるのですが、詳細を見る限り、エレコムさんは10年分まとめて支払う方針で権利化しているようです。
32,900円×合計69区分=2,270,100円(227万円)
更新手数料も高い
2022年に更新をした権利(区分数)を調べる方法が「全部の公報を見る」しか思いつかなかったので、妥協して記事執筆時点で「出願・権利存続中」ステータスになっている権利に基づいて計算しました。該当するものは384件、合計515区分です。
さきほども説明したように、エレコムさんは10年分まとめて登録料を支払い=10年ごとに更新をする方針です。
単純計算で全体の1/10にあたる51.5区分、小数点を四捨五入して52区分が更新時期に差し掛かっています。このうちの6割、だいたい31区分の権利を存続させると仮定しました。
43,600円×合計31区分=1,351,600円(135万円)
弁理士への手数料
最後に、弁理士への手数料を算出しましょう。
商標出願の手数料は区分数をはじめとした多くの要素で決定し、なおかつ権利化のために追加の手続き(中間処理)が発生する場合もあります。ようするに、これまで通りに目安費用から1.2倍した金額を出しました。
10万円×18件×1.2=2,160,000円(216万円)
商標権に使った金額は…
370,800円+2,270,100円+1,351,600円+2,160,000円=6,152,500円
と、特許権の倍以上の予算を商標権に使っている模様です。
特許を取るには最低60万円必要なので特許=出費が高額、というイメージがあるかもしれませんが、ちりも積もればなんとやら。件数の多さは必要予算の多さに直結しているのがよく分かりました。
ついに最後の計算。エレコムが1年間で知財にあてた予算は?
皆さん大変長らくお待たせいたしました。エレコムが2022年に知財に使った予算総額を算出していきましょう!
特許2,627,000円+意匠18,987,400円+商標6,152,500円=総額27,766,900円
権利化と権利の維持だけで約2777万円!
このほかにも特許調査費用やライセンス代、更なる追加の弁理士費用や弁護士への相談・依頼料が発生することも考えると、なかなか凄い金額になりそうです。
また今回は外国出願の費用を考慮にいれていないので、権利維持に今回の計算以上に予算を充てている可能性が大いにあります。
そういった諸々を考えると、1年で知財に5,000万円くらい使っていても全くおかしくないでしょう。ライセンス料等次第では、1億円近くになることがあるかもしれませんね。
まとめ
みなさんは「エレコムは1年で2700万円を知財に使ってます」と聞いてどう感じたでしょう?
高いと感じたか、意外と少ないと感じたか。
編集部個人としては、大手企業ってこんなに知財に予算充ててるんだと思いました。
ただ今回の計算には沢山の部分で妥協をしているので、リアルではどれくらいの金額になるのかが気になるところです。
それから、キヤノンやトヨタのような、特許権に力を入れている企業になるとこの金額がどこまで跳ね上がるのか……なんてことも気になりますね。
当初の予想の10倍は計算が大変でしたが、知財はこれだけの予算を割く価値がある、そう判断されるくらい大切なものだ、ということが伝わったならば嬉しいです。
あなたの技術に強い弁理士をご紹介!

