未管理の著作物を使用するための裁定制度について解説します
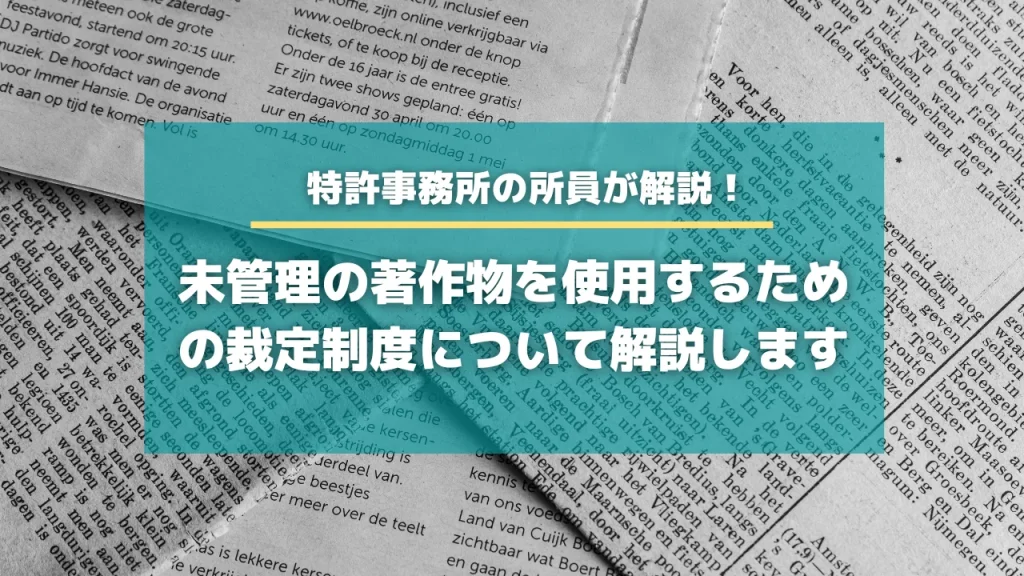
著作物を利用するにあたっては、著作権者からの許諾が必要です。しかし、著作物の著作権者が不明である(未管理の著作物である)場合には、著作権者から許諾を得ることが困難となり、その結果、著作物を利用できないということも考えられます。
このような事案に対応するため、現行(2025年時点)の著作権法には「裁定制度」が設けられており、一定の条件の下、補償金を文化庁に供託することで、未管理の著作物を利用することができるようになっています。
しかしながら、現行の裁定制度は裁定を受けることが難しい制度となっているため、条件見直しが求められていました。
今回は、2026年春ごろから施行される予定の「未管理著作物裁定制度」について、解説します。
未管理著作物裁定制度とは?
未管理著作物裁定制度(著作権法第67条の3)とは、未管理の著作物について利用を希望しているものの、著作権者の意思を確認できない場合に、利用希望者が文化庁に補償金を供託することで、裁定を受けることのできる制度です。
未管理の著作物を対象としているため、著作権者が不明であるときに用いることができます。
ただし、著作権者の意思が確認できない間の時限的な利用を認める制度であり、利用期間には3年の上限が設けられています。
また管理されている著作物(著作権者を特定することができる)については、改正後の著作権法第67条に規定される裁定制度で、引き続き対応することになります。
【改正前の著作権法第67条 第1項】
第六十七条 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することができる。
【改正後の著作権法第67条の3 第1項】
第六十七条の三 未管理公表著作物等を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管理公表著作物等を利用することができる。
一 当該未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置として文化庁長官が定める措置をとつたにもかかわらず、その意思の確認ができなかつたこと。
二 著作者が当該未管理公表著作物等の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。
【改正後の著作権法第67条 第1項】
第六十七条 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかである著作物(以下この条及び第六十七条の三第二項において「公表著作物等」という。)を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該公表著作物等を利用することができる。
一 権利者情報(著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他著作権者と連絡するために必要な情報をいう。以下この号において同じ。)を取得するための措置として文化庁長官が定めるものをとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有する全ての権利者情報に基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつたこと。
二 著作者が当該公表著作物等の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。
引用:著作権法の一部を改正する法律 新旧対照条文(文化庁)
※太字部分筆者
※改正後の著作権法第67条の3 全文は記事の最後に掲載しています
現行の裁定制度
現行の裁定制度は、作権者が不明である場合において、相当な努力を払っても著作権者と連絡をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受けて、使用料相当額の補償金を供託することにより、著作物を利用することができる制度です(現行の著作権法第67条)。
現行の裁定制度において、裁定が認められる要件は、次の通りです。
- 公表された著作物である
- 相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができない
- 使用料相当額の補償金を供託する
現行の裁定制度の問題点
現行の裁定制度は、「相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができない」の要件が厳しく、裁定を認めるケースが非常に少ないという問題があります。
この「相当な努力」については、著作権法施行令において、次の1-3の全ての措置を取ったにも関わらず、著作権者と連絡を取ることが出来なかった場合と規定されています。
- 広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧すること。
- 著作権等管理事業者その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定める者に対し照会すること。
- 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方法により、公衆に対し広く権利者情報の提供を求めること。
簡単に言えば「指定の刊行物を確認し、著作権管理者として知られている相手に連絡し、新聞に権利者情報提供のお知らせ掲載」を全てして、それでも著作権者と連絡を取れなかったとき、初めて現行の裁定制度が利用できます。
未管理著作物裁定制度の対象
未管理著作物裁定制度の対象は、以下の要件を全て満たす著作物です。
- 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供等されている事実が明らかである
- 著作権等管理事業者による管理が行われていない
- 著作物の利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報であって文化庁長官が定めるものが公表されていない(利用可否や条件等の明示がない)
したがって、著作権等管理事業者(JASRAC等)によって集中管理されている著作物は裁定の対象外となります。
未管理公表著作物裁定制度の要件
未管理著作物裁定制度の利用が認められるための要件は以下の通りです。
- 著作権者の意思を確認するための措置として文化庁長官が定める措置をとったにも関わらず、意思の確認ができない
- 著作者がその未管理公表著作物の利用を廃絶使用としていることが明らかでない
- 文化庁長官の定める額の補償金を供託する
- 著作物の題号、利用方法及び利用期間等を記載した申請書と、未管理公表著作物であることを疎明する資料などを文化庁長官に提出する
この申請書の提出や要件の確認、補償金の受領・管理等については、文化庁長官による指定・登録を受けた民間機関が、窓口となって対応することが可能となっています。またこの民間機関では、利用者の窓口となって手続を担うことが可能となっています。
要件を満たした場合の効果
未管理公表著作物におけるこれらの要件が認められた場合、利用を認める旨の裁定がなされます。
この裁定では、著作物の利用方法、利用期間などが定められます。その際、利用期間については、裁定の申請書に記された期間内でかつ3年以内の期間が定められます。
また、著作物の利用方法と利用期間については公表されます。
ただし、裁定が認められた場合でも、著作権者からの意思表示があれば裁定を取り消すことは可能です。そして、この取り消しの手続をする際には、裁定を受けた者に対して弁明の機会が与えられます。
補償金について
未管理公表著作物の裁定で供託する補償金の金額は、通常の使用料を考慮して定められます。
また、裁定による利用期間中に裁定が取り消しされた場合には、著作権者は、裁定された日から取り消しされた日の前日までの期間の使用料に相当する金額を、供託された補償金から受け取ることができます。
どんなときにこの制度が使われるか?予想される事案
未管理公表著作物の裁定が用いられるであろうと予想される事案としては、例えばJASRAC等の著作権管理事業者団体で管理されていない著作物であって、著作権者との連絡がつかない場合に、未管理公表著作物の裁定を用いることで、著作物を利用する、ということが挙げられます。
また著作権者が既に無くなっていて、遺族との連絡がつかない場合にも、未管理公表著作物の裁定を用いることで、著作物を利用する、ということが考えられます。
現時点での問題点
未管理公表著作物の裁定では、著作権者が著作権についての利用可否や条件等の明示をしておらず、かつ、利用を希望している者からの問合せに応答しなかった場合には、裁定により著作物が利用されるおそれがあります。
そのため、著作権者が問合せに対して偶然にも気づかなかった場合には、いつの間にか他人に著作物を利用されている、ということも起こりえます。
まとめ
未管理公表著作物の裁定制度は、著作権者の連絡先がわかるものの、著作物の利用の可否について意思を確認することができない場合についても裁定を可能にする制度であり、著作物をより利用しやすくした制度であるといえます。
その一方で、この裁定制度では、著作権者の知らない間に裁定が認められ、著作物が利用される、という事態を招く可能性もゼロではありません。
このような裁定による利用を未然に防ぐため、ウェブサイトやSNS等で、利用禁止の旨の記載や利用条件を掲載する等の対策をする必要があるでしょう。
【改正後の著作権法第67条の3(全文)】
第六十七条の三 未管理公表著作物等を利用しようとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当する額を考慮して文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管理公表著作物等を利用することができる。
一 当該未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置として文化庁長官が定める措置をとつたにもかかわらず、その意思の確認ができなかつたこと。
二 著作者が当該未管理公表著作物等の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかでないこと。
2 前項に規定する未管理公表著作物等とは、公表著作物等のうち、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。
一 当該公表著作物等に関する著作権について、著作権等管理事業者による管理が行われているもの
二 文化庁長官が定める方法により、当該公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報であつて文化庁長官が定めるものの公表がされているもの
3 第一項の裁定(以下この条において「裁定」という。)を受けようとする者は、裁定に係る著作物の題号、著作者名その他の当該著作物を特定するために必要な情報、当該著作物の利用方法及び利用期間、補償金の額の算定の基礎となるべき事項その他文部科学省令で定める事項を記載した申請書に、次に掲げる資料を添えて、これを文化庁長官に提出しなければならない。
一 当該著作物が未管理公表著作物等であることを疎明する資料
二 第一項各号に該当することを疎明する資料
三 前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める資料
4 裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該裁定に係る著作物の利用方法
二 当該裁定に係る著作物を利用することができる期間
三 前二号に掲げるもののほか、文部科学省令で定める事項
5 前項第二号の期間は、第三項の申請書に記載された利用期間の範囲内かつ三年を限度としなければならない。
6 第六十七条第四項及び第六項から第十項までの規定は、裁定について準用する。この場合において、同条第七項第一号中「第五項各号」とあるのは「第六十七条の三第四項各号」と、同条第八項第二号中「第五項第一号」とあるのは「第六十七条の三第四項第一号及び第二号」と読み替えるものとする。
7 裁定に係る著作物の著作権者が、当該著作物の著作権の管理を著作権等管理事業者に委託すること、当該著作物の利用に関する協議の求めを受け付けるための連絡先その他の情報を公表することその他の当該著作物の利用に関し当該裁定を受けた者からの協議の求めを受け付けるために必要な措置を講じた場合には、文化庁長官は、当該著作権者の請求により、当該裁定を取り消すことができる。この場合において、文化庁長官は、あらかじめ当該裁定を受けた者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
8 文化庁長官は、前項の規定により裁定を取り消したときは、その旨及び次項に規定する取消時補償金相当額その他の文部科学省令で定める事項を当該裁定を受けた者及び前項の著作権者に通知しなければならない。
9 前項に規定する場合においては、著作権者は、第一項の補償金を受ける権利に関し同項の規定により供託された補償金の額のうち、当該裁定のあつた日からその取消しの処分のあつた日の前日までの期間に対応する額(以下この条において「取消時補償金相当額」という。)について弁済を受けることができる。
10 第八項に規定する場合においては、第一項の補償金を供託した者は、当該補償金の額のうち、取消時補償金相当額を超える額を取り戻すことができる。
11 国等が第一項の規定により未管理公表著作物等を利用しようとするときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定による供託を要しない。この場合において、国等は、著作権者から請求があつたときは、同項の規定により文化庁長官が定める額(第八項に規定する場合にあつては、取消時補償金相当額)の補償金を著作権者に支払わなければならない。
特許事務所に勤務している弁理士です。中小企業のクライアントを多く扱っています。特許業務が主ですが、意匠・商標も扱います。
あなたの技術に強い弁理士をご紹介!

