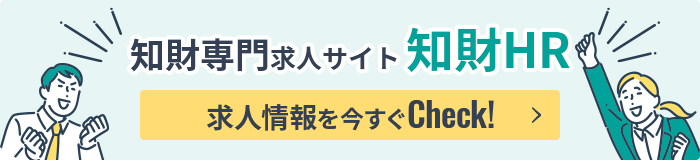ゲーム判例シリーズ〜入門編〜-iP Times.-
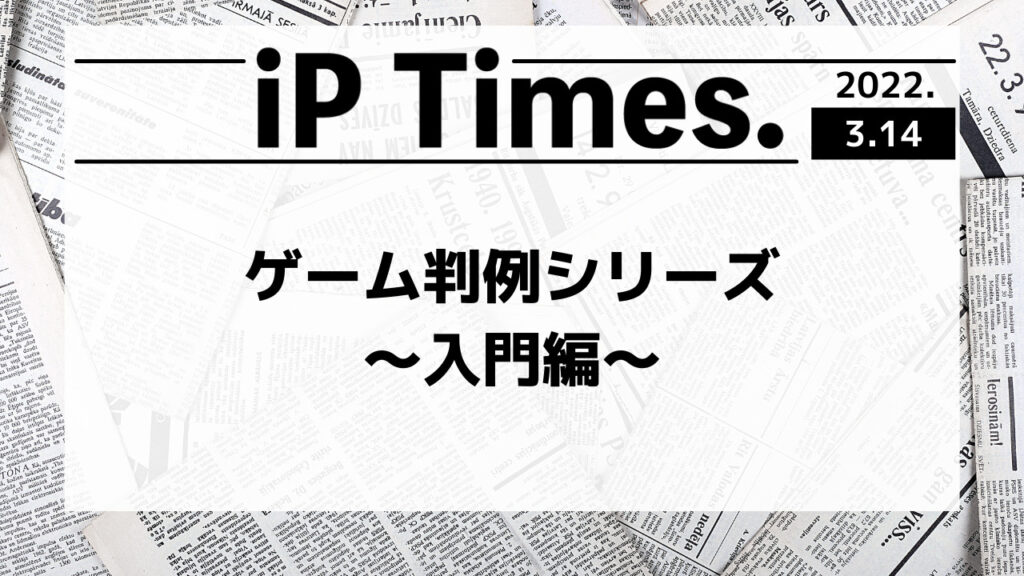
(この記事は、2022年3月14日に商標専門弁理士が作成したものです。)
こんな方に向けた記事です。
☆弁理士受験生や法学部などで知的財産法を勉強中の方へ
☆気になる判例をチェックしている方へ
☆ゲーム界隈で少しだけ判例に詳しい人になりたい方へ
本記事のここがポイント!!
法律を学ぶ上で最重要と言っても過言ではない裁判所の判断=判例。その判例はどんな働きをするのか?を解説します
判例の意義とは?
ゲーム関連する判例を紹介するシリーズ。
まずは、入門として何故判例(裁判所の判断)が必要なのか?を解説します!
初っ端から、なんだか難しそうな単語の羅列……ムズカシそう。
しかし、そこは「知財を身近に!」をスローガンに掲げるiP Times。
できるだけ分かりやすい文章や内容、また皆さんの興味をもてるような題目をご用意しますので、ぜひおつきあいください!
さあ、早速ですが、なぜ裁判所での争いがあるのでしょうか。
もちろん、そこに争いがあるからではあるのですが、大きく分けて3つのことが考えられます。
1、条文に記載がされていない事項で争いが起きているから
2、条文上の単語の解釈がはっきりしないから
3、条文通りの適用では妥当ではないケースがあるから
条文というのは、いつの時代も完璧な存在であるということはありえません。
そもそも、規定がないケースもあれば、単語の解釈が複数通り考えられるケースもある。よって、争いが生じ、裁判所に判断してもらうということになるのですね。
例えば、どんなケースがあるの?
商標の分野では以下のようなケースがありました。
これは、上述のパターンでは3、に該当するものです。
例えば、
Aさん 商標「野菜」 指定商品「ダンボール」で商標権を持っている
Bさん 「野菜」の語を「ダンボール」に使用してしまった
というケース
ま、これは普通に条文上から考えれば、商標権の侵害になるケースです。
但し、これが、ダンボール内の中身を示すだけの「野菜」だった場合はどうか?
これは、誰がどう見ても、商標的に使用しているより「中身が野菜ですよー」を示しているにすぎないと思いませんか。確かに、形式的には他人の商標を使用してしまっているが、これを商標権の侵害と判断するのは妥当ではない。
このような判断もありました。
(※商標「巨峰事件」もモデルケースに作成しました。)
まとめ
まずは、判例とはどういうものなのかをざくっと見てきました。
次回から、ゲーム判例シリーズの本題に入りますので、お楽しみに。


弁理士歴7年。商標調査の件数は、5200件を突破しました。 商標のニュースは常に気になり、商標をこよなく愛する商標好きの 事務所勤務の弁理士です。好きな商標の言葉は、登録査定。
Twitter:@syohyosuki
まずは気軽に無料相談を!