医薬品分野の特許とは?
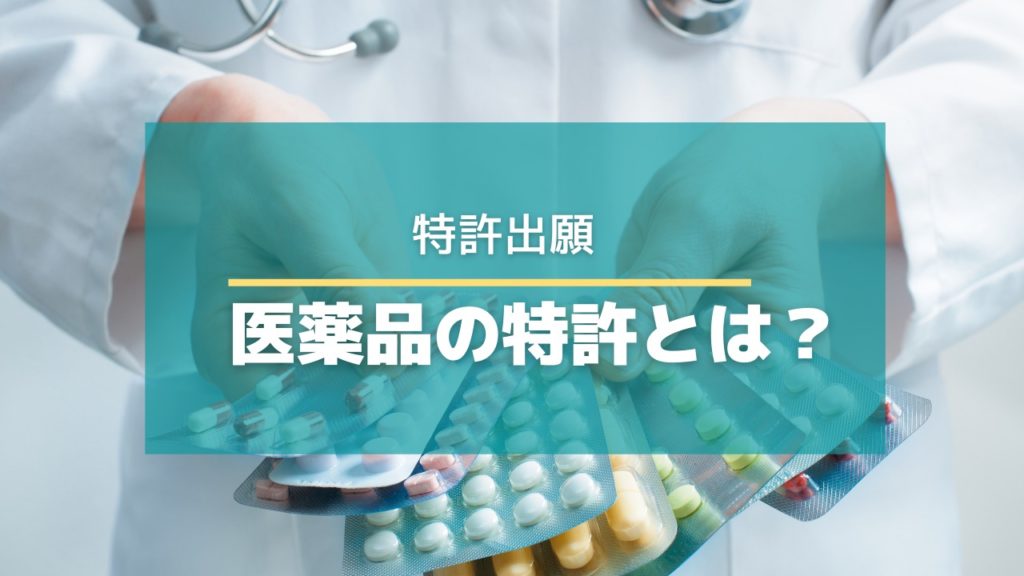
医薬品分野の特許は、他の分野の特許と比べて、特許権取得による収益が非常に高いという特徴があります。その理由として、医薬品は、監督官庁の許可等がなければ、販売、製造等をすることができないため、他社との価格競争となる要因が少ない、という医薬品特有の事情が挙げられます。
その一方で、医薬品分野では、特許権満了後に、会社全体の売上が大きく減少するという特徴があります。
今回は、このような医薬品分野の特許特有の事情について解説します。
医薬品特許の種類
医薬品特許には、物質特許、用途特許、製剤特許、製法特許の4種類があります。各特許の特徴は、次のようになっています。
物質特許
物質特許とは、新薬開発にて生じた、新たな物質(特に化合物)に付与される特許を指しています。物質特許は、医薬品特許の中でも最も権利の範囲が広く、物質特許を持つ企業は、開発した医薬品を独占的に販売する権利を有することになります。
物質特許の例としては、抗がん剤「レンバチニブ」があります。レンバチニブは、がんの成長や転移に関与する複数の酵素を同時に阻害することで、抗腫瘍効果を発揮する医薬品です。
用途特許
用途特許とは、既存の物質に新たな用途が発見された場合に、その用途について付与される特許のことです。すなわち、特許権が付与された新たな用途以外の用途に用いた場合には、用途特許の効力は及びません。
用途特許の例としては、解熱剤である「アセチルサリチル酸」(アスピリン)を、心筋梗塞や脳梗塞の予防に利用した特許があります。
製剤特許
製剤特許とは、医薬品を製剤する過程で発見した技術、具体的には、製剤の安定性や有効成分の吸収性等について付与される特許のことです。
製剤特許の例としては、抗体医薬品の凍結乾燥(リオフィル)製剤による長期保存に関する特許があります。
製法特許
製法特許とは、医薬品の新しい製造方法、例えば合成方法や製造手順についての特許です。製法特許の例としては、タミフル(オセルタミビル)を人口合成経路による改良法により、収率を向上させた特許があります。
医薬品特許の特徴
医薬品特許は、特に物質特許において、非常に多くの外国に出願することが他分野の特許と大きく違います。
そのため、外国も含めた特許権取得費用も数千万円、案件によっては1億円以上となります。
また医薬品の販売には薬事承認を受ける必要があるため、この承認に要する期間と特許権の存続期間との調整規定が設けられています。
外国出願の出願先が多い
医薬品は非常に多くの国で使用されるため、医薬品の特許、特に物質特許は多くの国で権利化を取得する傾向があります。
例えば抗がん剤「レンバチニブ」(特許第6659554号)の特許は、日本のほか、ヨーロッパ、北米、アジア、中南米、オセアニアの諸国などに出願されています。
特許権の期間を延長する制度(延長登録出願)がある
医薬品を販売するにあたっては、薬事承認を申請し、厚生労働大臣と薬事・食品衛生審議会による諮問を経て、承認を受ける必要があります。
しかしながら、薬事承認の申請から承認までの間には、審査を行う部署の調査や面談が行われるため、事案によっては特許権の設定登録から承認を受けるまでの期間、医薬品を販売することができない、ということも起こりえます。
そこで許法では、設定登録から承認を受けるまでの期間について、5年を限度として、延長することができる制度が設けられています(特許法第67条4項)。
(存続期間)
第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
4 第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。)は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
特許権の効力の及ばない範囲がある
また特許法では、特許権の効力が及ばない行為として、次の行為を規定しています。
- 試験又は研究のためにする特許発明の実施(特許法第69条1項)
- 医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為(特許法第69条3項)
- 医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬(特許法第69条3項)
なお他社が製造販売承認申請をするために医薬を製造する行為は、「試験又は研究のためにする特許発明の実施」になるため、特許権の効力は及ばない、と裁判所は判断しています(最高裁第二小法廷平成11年4月16日判決・平成10年(受)第153号)。
これはもし仮に、医薬品の治験が特許権侵害にあたるとすると、特許権の存続期間が終了した後もなお相当の期間、第三者が実施できない結果となるからです。
特許権満了後の医薬品について
特許権満了後は、特許権で保護されていた医薬品と同様の医薬品を、他の製薬会社がジェネリック医薬品として製造・販売することができます。そのため、医薬品における特許権の満了後は、売上が大幅に減少します。
ジェネリック医薬品とは
ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同じ有効成分を使っており、品質、効き目、安全性が同等な医薬品です。
ジェネリック医薬品の特徴としては、先発医薬品よりも開発費や開発期間が少ないため、先発医薬品よりも安価で販売できることが挙げられます。
また2024年10月から、ジェネリック医薬品のある先発医薬品を希望した場合には、自己負担額が増加しており、この点からもジェネリック医薬品は先発医薬品よりも安価となっています。
パテントクリフ
パテントクリフとは日本語で「特許の壁」を意味する用語です。医薬品の分野では、物質特許の特許権が満了すると、会社の売上が大幅に減少することから、この売上減少が予測される時期のことをパテントクリフと呼んでいます。
例えば、ファイザー株式会社では、脂質異常症の治療薬であるリピトールの物質特許を有しており、このリピトールは2011年度には世界で約9000億円の売上を得ていました。しかし、2011年に米国での特許が失効したため、2014年度には世界での売上が約2000億円まで落ち込みました。
またエーザイ株式会社は、アルツハイマーの治療薬であるアリセプトの物質特許を有しており、このアリセプトの特許権を有していた2009年度には約8000億円の売上を得ていました。しかし2010年以降、アリセプトの特許権が失効したため、エーザイ株式会社の売上は2012年度で6000億円を切るところまで減少しました。
このことから、医薬品における物質特許の有無は、会社の売上に大きく影響することがわかります。
関連記事
完全無料で事務所選びをサポートします
まずはお気軽にお問合せください!
あなたの技術に強い弁理士をご紹介!

