著作物の私的利用について解説します
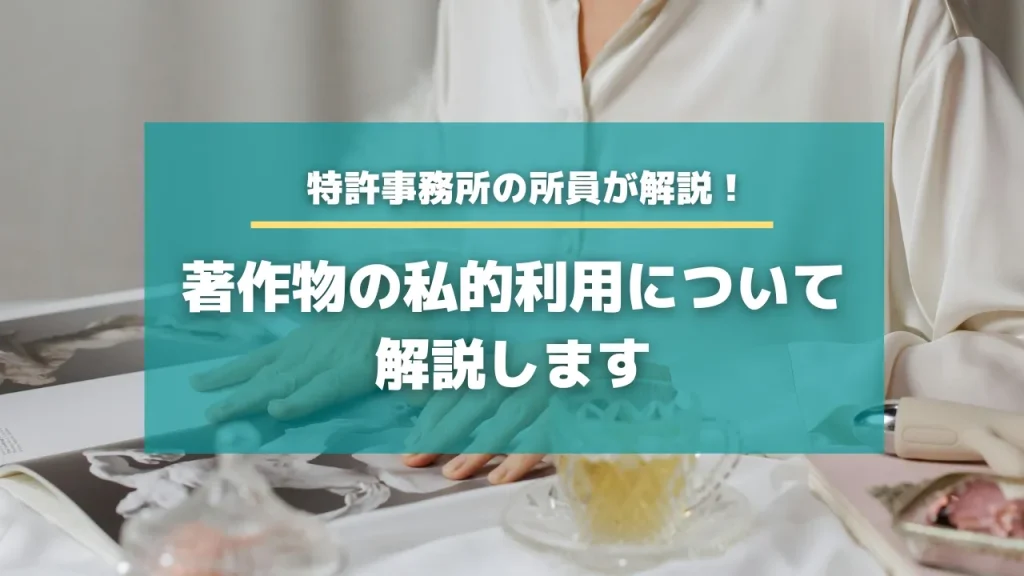
他人の著作物を利用するにあたっては、原則として著作権者の許諾を得るか、又は著作権を譲渡してもらうことが必要となります。
しかし、ごく個人的な使用(私的使用)、引用、学校教育の目的など、著作物の利用形態によっては許諾なしで著作物を利用することができます。
今回は著作権者の許諾を受けることなく、利用することのできる形態のうち、私的使用を中心に解説します。
著作物の私的利用とは
著作物の私的利用とは、著作物を個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(私的使用)を目的とする場合は、一定要件下で、その使用する者による複製を認めることです(著作権法第30条1項)。
この規定の立法趣旨としては、限られた範囲の複製であるため権利者への影響が少ないこと、権利者と複製者との交渉の場がないため交渉が困難であることが挙げられます。
私的利用として認められる行為
著作物の私的使用は、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する」ことを目的としています。
そのため、企業などの内部で使用する目的での複製は私的利用に該当しないと考えられています。
また著作物の私的使用では、「その使用する者による複製」が認められています。すなわち、著作物の私的使用は、私的使用をする本人が複製をする場合に限り許されます。
ただしこの”複製”については、翻訳や変形、又は翻案も含んでいます(著作権法第47条の6第1項第1号)。
グッズに著作物を利用した場合
グッズに著作物を利用した場合、自分でグッズを使用する限りでは、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内における使用に該当するため、著作権者の承諾は不要です。
ただしSNSやYouTubeなどでグッズを公開する行為は、著作権法上の複製ではなく公衆送信に該当するため、認められません。
またグッズを自ら製作せず、業者に依頼する行為も「その使用する者による複製」に該当しないため、この行為も認められません。
個人的に又は家庭内等において使用することを目的とする複製
先ほど述べたように著作権法では、個人的に又は家庭内等において使用することを目的とする複製は、一定条件のもと認められています。
しかしながら、公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合には、私的利用であっても著作物を利用することができない旨の規定があります(著作権法第30条第1項第1号)。
ここで、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」としては、コンビニエンスストアなどに置いてあるコピー機等が挙げられます。そのため条文からは、この種のコピー機で書籍等をコピーする行為が認められない、とも読み取れます。しかし、著作権法の附則には、次の規定が設けられています。
第5条の2 著作権法第30条第1項第1号及び第119条第2項第2号の規定の適用については、当分の間、これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。
従って、コピー機で書籍をコピーし、このコピーを私的利用の範囲で使用することは認められています。
デジタル方式の補償金制度
私的利用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器を使い、テレビなどで放映された番組(動画)を録音又は録画をする場合、一定の条件の下、相当額の補償金を著作権者に支払う必要があります(著作権法第30条第3項)。
デジタル方式の録音又は録画の機能を有する主な機器としては、次の機器があります。
- MDレコーダー
- CD-R方式のCDレコーダー
- CD-RW方式のCDレコーダー
- Blu—ray(ブルーレイ・ディスク)レコーダー
- Blu—ray(光ディスク)
私的利用として認められない行為
その一方で、個人的に又は家庭内等において使用することを目的とする行為であっても、場合によっては、著作物の利用が認められないこともあります。
次に、私的利用であっても著作権の侵害となる場合について説明します。
技術的保護手段回避による複製
技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う行為は、例え個人的に又は家庭内等において使用することを目的とする行為であっても、認められません(著作権法第30条第1項第2号)。
技術的保護手段の回避とは、いわゆるプロテクト外しを意味しています。例えば、技術的保護手段として、音楽CDの複製に制限をかけた手段や、複製をしても鑑賞に堪えられないような乱れた画像とする技術などを回避することが該当します。
違法サイトからのダウンロード
違法サイトからのダウンロードについて、次の1、又は2に該当する場合には、私的利用が認められません。
1.著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画(特定侵害録音録画)が、著作権を侵害しているものであることを知りながら行った場合(著作権法第30条第1項第3号)
この規定は例えば、インターネット上で配信されている音楽や動画が、違法にアップロードされていることを知っているにも関わらず、録音や録画をする行為は、認められないという規定です。
2.著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の複製を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合(著作権法第30条第1項第4号)
この規定は、「海賊版」にあたる漫画・書籍・論文・コンピュータープログラム等のダウンロードを、海賊版と知りながら行う行為は、認められないという規定です。
そのほか、著作物の複製が許されている例外事項
学校の授業等で著作物を用いる場合には、著作権者の許諾を得ずに、著作物を使用できる場合があります。具体的には、以下の場合です。
① 教科用図書への掲載(著作権法第33条第1項)
教科用図書に著作物を掲載するにあたっては、著作権者の許諾は不要です。ただし、この場合には、一定の補償金を著作権者に支払う必要があります(著作権法第33条第2項)。
②学校教育番組の放送(著作権法第34条第1項)
公表された著作物については、著作権者の許諾を得ることなく、教育番組において放送することができます。ただし、教育番組で放送する旨を著作者に通知し、かつ、所定の補償金を著作権者に支払う必要があります(著作権法第34条第2項)。
③学校その他の教育機関における複製等(著作権法第35条第1項)
学校その他の教育機関における教員及び生徒は、授業の必要な範囲で、複製や、公衆送信をすることができます。ただし、公衆送信をする場合には、所定の補償金を著作権者に支払う必要があります(著作権法第35条第2項)。
著作権に関する記事
- 教えて柴田先生!キャラクターの商標権・著作権を侵害した判例って?
- 教えて柴田先生!SNSで音楽をアップするとダメなの?
- 教えて柴田先生!キャラクターの権利はどうやって保護する?
- 教えて柴田先生!著作権って何?
- 教えて柴田先生!Twitterで気を付けることって?
完全無料で事務所選びをサポートします
まずはお気軽にお問合せください!
特許事務所に勤務している弁理士です。中小企業のクライアントを多く扱っています。特許業務が主ですが、意匠・商標も扱います。
あなたの技術に強い弁理士をご紹介!

