商標登録に大きく関わる!商標の類似群コードについて解説
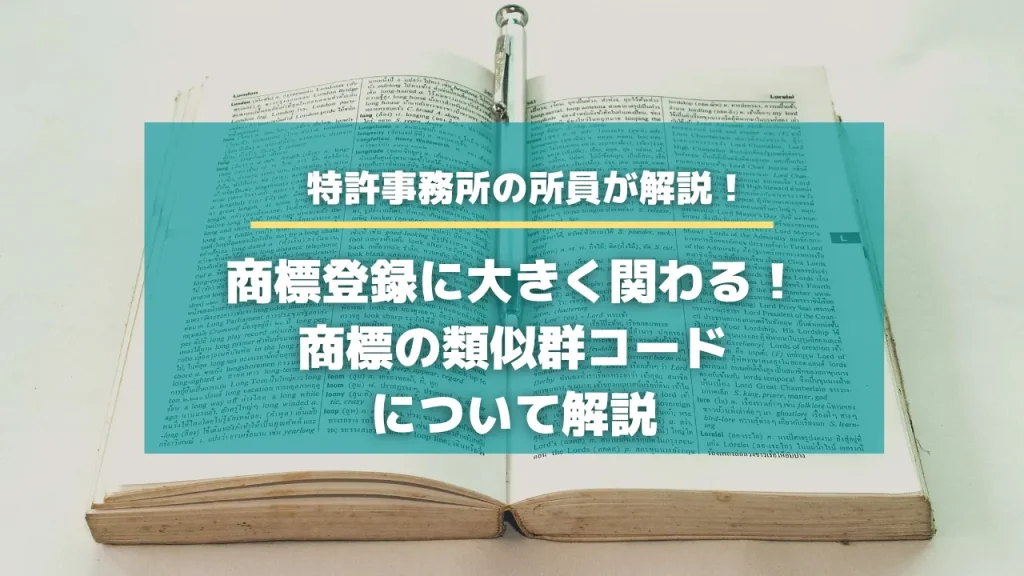
類似群コードとは
類似群コードとは、商品やサービスが、互いに類似しているか否かを区別するために付けられた番号です。比較した2つの商品やサービスの類似群コードが同じである場合、特許庁は原則として両者を類似と判断します。
例えば、指定商品「調理用具」(類似群コード:19A05)について、商標「ABCXYZ」を出願したところ、既に「家庭用食品包装フィルム」(類似群コード:19A05)について、商標「ABCXYZ」が商標登録をされている場合には、商品が互いに類似し、商標が同一であるため、出願した商標に拒絶理由が通知されます。
ただし、類似群コードは特許庁による商品・サービスの類否に用いられるコードであり、裁判所における商標権侵害の可否では使用されません。
公報にも掲載される
類似群コードは、指定商品と共に、商標公報に掲載されます。
例えば、タリーズコーヒーの持っている商標の商標登録第6683962号の公報では、指定商品が「第30類 コーヒー、コーヒー飲料」で類似群コードが「29B01」であることが掲載されています。
類似商品・役務審査基準とは
類似商品・役務審査基準とは、商品やサービスの類否関係を一定の基準に基づいて検討し、その類否関係を整理したものです。類似商品・役務審査基準には、各区分に該当する商品・サービスと、商品・サービスに対応した類似群コードが記載されています。
なお類否関係の基準は、商品の生産部門・販売部門、原材料・品質や、サービスを提供する手段・目的・場所などに基づいて定められています。
類似商品・役務審査基準は特許庁のホームページに掲載されており、書籍でも販売されています。
類似商品・役務審査基準 国際分類第11-2022版対応 (類似商品役務審査基準)(Amazon)
類似商品・役務審査基準はこまめに更新される
類似商品・役務審査基準は平成24年以降毎年更新されています。例えば、類似商品・役務審査基準(第12-2023版)では、以下の追加、変更等がなされています。
- 第30類に「料理⽤⼈⼯⽢味料」(31A03)を追加
- 第26類の「ミシン針」(13A02)を第7類に変更
違う区分でも類似する?
商標の区分とは、特許庁が定めた商品やサービスのカテゴリーを意味しています。第1類が触媒などの化学品、第2類がインクなどの塗装・着色剤…といった感じに分かれており、区分が異なる=カテゴリーが異なるため、「区分が異なる商品・サービスは原則として非類似の関係」になります。
ちなみに商標の区分は第1類から第45類まであり、第1類から第34類までが商品、第35類から第45類までがサービスとなっています。
しかし異なる区分であっても、商品の生産部門・販売部門、原材料・品質や、サービスを提供する手段・目的・場所などの様々な要素を考慮し、互いに類似するとされている商品・サービスもあります。
【基礎知識】類似群コードと区分の違い
類似群コードは、商品やサービスが互いに類似しているか否かを区別するために付けられたコードであるため、商標の類否判断に影響するという特徴を有します。
一方で、区分の特徴としては、出願時や登録時に特許庁に納付する金額が変わることが挙げられます。
商標登録出願時の納付金額は、3,400円+(区分数×8,600円)です。そのため区分が1つだと出願時の納付金額は12,000円となり、区分が3つの場合には出願時の納付金額は29,200円となります。
また登録時の納付金額は、区分数×32,900円であるため、区分数に乗じて、納付金額が増える仕組みになっています。
違う区分で類似する例
違う区分で類似する例としては、第21類の「調理用具」と第16類の「家庭用食品包装フィルム」には、共に類似群コードとして19A05が付与されており、両者は異なる区分の商品であるにも関わらず、互いに類似の関係であるとされています。
また、第30類の「コーヒー」と、第35類の「コーヒーを主原料とする調製品及びコーヒー飲料の小売店の業務において行われる顧客に対する便益の提供」には、共に類似群コードとして29B01が付与されており、商品とサービスの間でも類似することがあるとされています。
類似群コードの調べ方
類似群コードの調べ方としては、類似商品・役務審査基準の他にも、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を用いて調べることが可能です。
J-PlatPatの商標検索の中には、商品・役務名検索があり、この検索における「商品・役務名」の欄に、商品・サービスの名称を入力すると、入力したキーワードを含む商品名・役務名が、区分とともに表示されます。
例えば、この「商品・役務名」の欄に「消しゴム」と入力すると、以下のように表示されます。
類似群コードにまつわる注意点
出願時の類似群コードの数によっては拒絶理由通知が発行される
出願時に指定する商品・サービスは、実際に使用するか、又は使用する予定のある商品・サービスに限られています。
したがって、指定する商品・サービスが1つの区分の中で多数ある場合には、拒絶理由を通知して、出願人に使用又は使用する予定について、カタログやパンフレットの提出などによる説明を要求するという運用をしています。
この拒絶理由に基づく確認の目安は、1区分内において、22個以上の類似群コードが記載されている場合となっています。
特許事務所に勤務している弁理士です。中小企業のクライアントを多く扱っています。特許業務が主ですが、意匠・商標も扱います。
まずは気軽に無料相談を!

